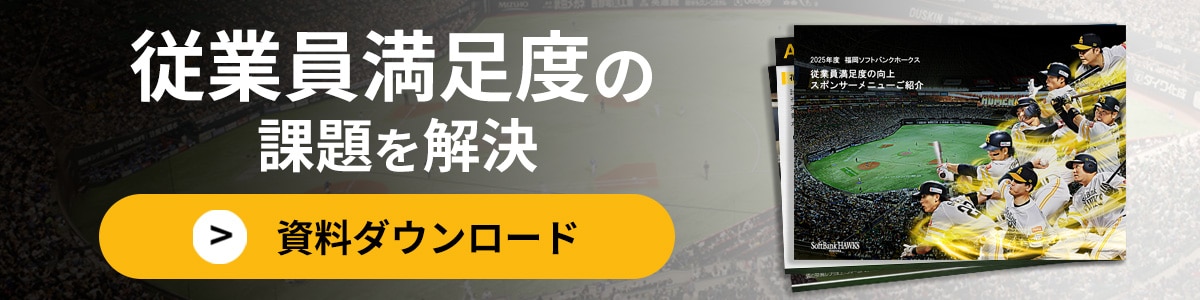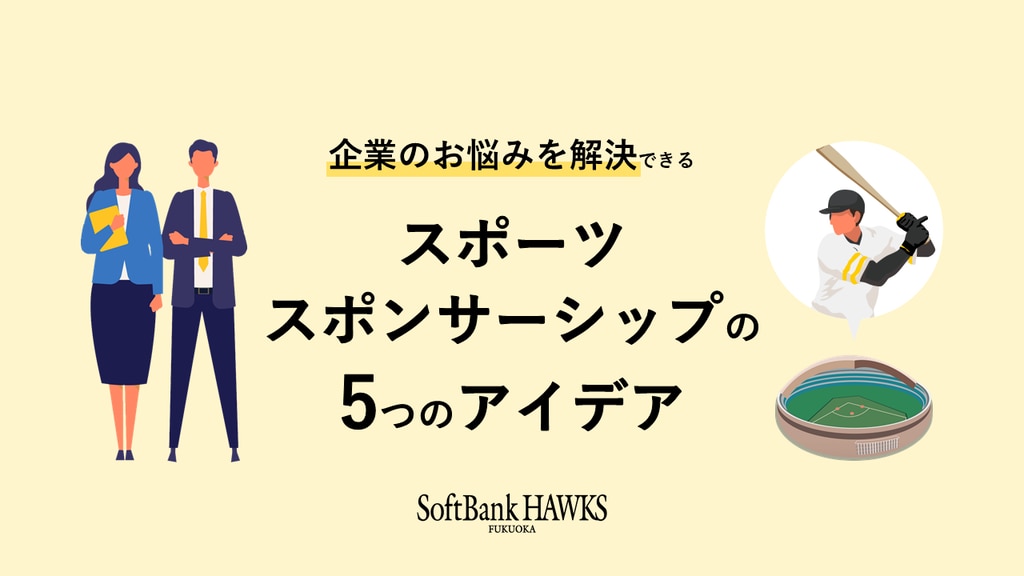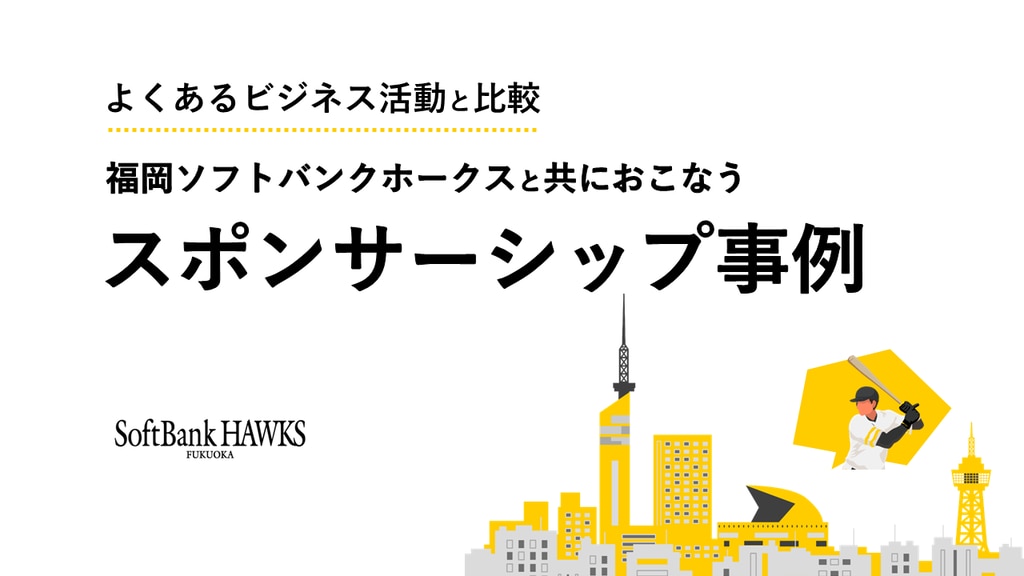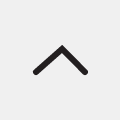インナーブランディングとアウターブランディングの違いとは? それぞれの施策で実現する企業価値の向上

企業ブランドを高めるためには、社内と社外の両方向からの取り組みが必要です。その中心にあるのがインナーブランディングとアウターブランディングです。従業員に理念や価値観を浸透させることで社内の一体感を強化しつつ、外部に向けたブランド発信で社会的認知や信頼を獲得する、この両輪がそろって初めて、企業は持続的な成長を実現できます。
本記事では、インナーブランディングとアウターブランディングの違いや目的、施策事例を整理し、福岡ソフトバンクホークスが提供するスポンサーメニューを通じてどのように両者を推進できるかを解説します。
>おすすめの記事はこちら
インナーブランディングの成功事例5選。プロ野球のスポンサーシップを活用する目的と効果
インナーブランディングとは。企業のメリットや効果的に取り組むポイント
目次[非表示]
インナーブランディングとアウターブランディングの違い
ブランディング活動は大きく分けて、社内向けの「インナーブランディング」と社外向けの「アウターブランディング」があります。
インナーブランディングは従業員に企業理念やビジョンを浸透させ、誇りや共感を育むことで離職率低下や従業員満足度向上につながります。
一方、アウターブランディングは顧客や社会にブランドを発信し、広告やPR、CSR、イベント協賛などを通じて認知度や信頼性を高め、売上増加や社会的評価の向上に寄与します。
両者は相互に補完し合う関係にあり、どちらか一方だけではブランド価値を最大化することはできません。
▼インナーブランディングとアウターブランディングの比較
項目 | インナーブランディング | アウターブランディング |
対象 | 社内(従業員) | 社外(顧客・取引先・社会) |
主な目的 | 理念の浸透、従業員エンゲージメント向上 | 認知度向上、顧客獲得 |
施策 | ワークショップ、社内報、クレドカード | 広告、PR、CSR、スポーツ協賛、SNS |
メリット | 組織力向上、離職率低下 | 売上増加、社会的信頼の獲得 |
成果指標 | エンゲージメントスコア、離職率 | 認知度調査、売上、メディア露出量 |
インナーブランディングは「企業文化の基盤をつくる活動」、アウターブランディングは「外部への信頼と認知を広げる活動」と整理できます。両方をバランスよく進めることで、企業のブランド価値は持続的に高まっていきます。
インナーブランディングが企業にもたらすメリットについてはこちらの記事でも解説しています。
インナーブランディングの進め方
インナーブランディングを効果的に進めるには、経営層の強いコミットメントと組織全体を巻き込む仕組みづくりが欠かせません。現状の課題を把握し、理念やビジョンを明確化したうえで発信・施策・改善を繰り返すことで、組織文化として根づいていきます。
インナーブランディング推進のステップ
インナーブランディングは一度きりではなく、継続的に定着させることが重要です。
▼推進の主な流れ
- 現状把握と課題分析理念や価値観がどの程度浸透しているかを調査する
- 経営層のリーダーシップ発揮経営層が自らの言葉で語り、従業員の共感を促す
- 施策の実施研修やワークショップ、意見交換イベントを定期的に実施する
- 効果測定と改善アンケートや離職率の変化を確認し、次の施策に反映する
このように段階的に取り組むことで、理念は「掲げるもの」から「行動基準」へと進化します。
効果的な発信方法
インナーブランディングは、どんなに理念がよくても伝わらなければ浸透しません。そのためには、経営層の発信に加えて、従業員が日常的に理念に触れ、意見を発信できる多様なチャネルを組み合わせることが大切です。
▼発信方法の例
- 経営層の発信トップメッセージや定例ミーティングを通じて理念を繰り返し伝えることで、組織の方向性を明確に示す
- 社内報・イントラネット記事や掲示を通じて従業員が理念に触れる機会を増やす
- 動画・社内SNS社員インタビューや事例動画を共有することで、理念に対する理解を深める
- 従業員の声を反映サーベイや提案制度を取り入れ、双方向のコミュニケーションを構築する
こうした取り組みを組み合わせることで、「上からの発信」だけでなく、従業員自身が主体的に参加できる仕組みが整います。結果として、理念は単なるスローガンではなく、現場で行動を支える基準として根づいていきます。
インナーブランディングの施策例
インナーブランディングは理念やビジョンを掲げるだけでは定着しません。日々の業務や従業員の行動に落とし込むために、複数の施策を組み合わせることが大切です。ここでは代表的な取り組みを紹介します。
研修・ワークショップ・社内イベント
理念を従業員に浸透させるには、「学ぶ」「考える」「体験する」という三段階が必要です。研修で知識を得て、ワークショップで自分の業務と結びつけ、社内イベントで仲間と共有するという流れが、理念を単なるスローガンではなく実践的な指針へと変えていきます。
▼各施策の内容と効果
施策 | 内容 | 期待できる効果 |
研修 | 新入社員や管理職向けに理念・ビジョンをテーマに実施 | 世代を超えて共通認識が定着 |
ワークショップ | グループで意見交換を行い、自分の業務と理念を結びつける | 相互理解が進み、実践への意欲が高まる |
社内イベント | スポーツ大会や表彰式、周年イベントなどを開催 | 交流が活性化し、一体感や帰属意識を醸成 |
こうした場を継続的に設けることで、従業員は理念を「体感」し、自発的に行動へ落とし込むようになります。
クレドカードの作成と活用
クレドカードは、企業理念や行動指針などを簡潔にまとめた携帯しやすいサイズのカードです。従業員一人ひとりが常に持ち歩くことで、単に「読むもの」ではなく、「日々の行動や判断に生かすもの」へと変えていきます。これにより、理念や行動指針が実務のなかで自然と生かされ、組織全体の一体感が高まります。
▼活用のポイント
- 従業員が持ち歩ける形にして、日常的に理念を意識できるようにする
- 意思決定に迷ったときの「判断基準」として活用する
- 市場や組織の変化に応じて定期的に内容を更新する
従業員はいつでもクレドカードを確認できるため、行動に迷ったときの判断基準となり、日常業務にも前向きに取り組めるようになります。結果として、仕事に対するモチベーションの向上や業務の質の改善にもつながります。
なお、現在ではホテル業界やIT業界などのさまざまな分野でクレドカードの導入が進んでいます。
インナーブランディングの効果測定とフィードバックの重要性
インナーブランディングの成否は、どれだけ理念が従業員に浸透し、行動に結びついているかで判断されます。そのためには、数字で裏づける定量的評価と、従業員の声から学ぶ定性的評価を組み合わせて効果測定を行い、その結果をフィードバックと改善に生かすことが重要です。
主な評価の種類と特徴は以下になります。
▼評価の種類・特徴
評価の種類 | 方法 | 特徴 |
定量的評価 | アンケート調査、エンゲージメントスコア、離職率の推移など | 数字で示せるため、経営層の納得感を得やすい |
定性的評価 | 従業員インタビュー、自由回答アンケート | 理念の理解度や実務での活用状況を把握できる |
評価結果は全従業員に共有し、課題や改善点を整理して次回施策に反映します。この“評価・フィードバック・改善”のサイクルを継続することで、インナーブランディングは単発の取り組みではなく、組織の基盤強化へと発展します。
アウターブランディングの重要性
アウターブランディングは、企業が社会や顧客に向けて“どのような存在でありたいか”を発信し、ブランド価値を外部から高める活動です。広告やPR、イベント協賛、SNS発信などを通じて企業やブランドをアピールすることで、イメージの向上や他社企業との差別化を図り、顧客の共感や信頼を獲得します。単なる認知拡大ではなく、企業のビジョンやブランド価値を伝えることが重要です。
アウターブランディングを成功させるには、まずブランドメッセージの明確化が欠かせません。自社の強みや社会的役割を整理し、“誰に、何を、どのように届けたいのか”を定義したうえで発信します。また、顧客や社会との接点となる広告、Webサイト、SNS、店舗体験など、複数のチャネルを組み合わせることも大切です。
アウターブランディングは、社会との接点で企業のブランド価値をどう表現するかが、信頼や共感を生む鍵になります。たとえば、以下の取り組みも効果的なアウターブランディングといえます。
▼アウターブランディングの例
- スポーツチームとのパートナーシップによる地域密着型の発信
- オフシーズンの選手が参加するイベント開催で体験価値を提供
- 顧客・ファンと共にブランドを育てるSNS発信やコミュニティ運営
なお、福岡でのブランディング施策については、こちらの記事をご確認ください。
福岡ソフトバンクホークスのインナー・アウターブランディングに貢献する施策
福岡ソフトバンクホークスのスポンサーメニューは、従業員満足度を高めるインナーブランディングと、社会的認知や信頼を拡大するアウターブランディングの両面で活用可能です。
インナーブランディングに貢献する施策
従業員が自社ブランドを誇りに思い、企業理念に共感することは、日々の業務へのモチベーション向上につながります。ホークスの施策は、この「誇り」と「一体感」を育む場として機能します。
▼鷹祭 SUMMER BOOST協賛を通じた従業員のユニフォーム着用

イベント協賛を通じて、インナーブランディングに貢献できます。日本航空株式会社では、『鷹祭 SUMMER BOOST』の期間中、福岡空港のカウンタースタッフもユニフォームを着用しました。社員が福岡ソフトバンクホークスのイベントの盛り上げに関わることが、モチベーション向上にもつながっています。
▼冠協賛(ゲームデースポンサー)

企業が試合を冠協賛することで、自社名が大舞台で大きく発信されます。顧客や従業員を試合に招待したり、始球式や花束贈呈などの特別な場面に参加できたり、従業員にとっては「自分の会社が公式の場に立っている」という誇りを実感できる機会となります。
▼スーパーボックス(VIPルーム)での野球観戦

みずほPayPayドームでの野球観戦を、社内交流の場として活用できます。従業員同士のリフレッシュや交流が深まり、チームワークや新しい発想の創出にも寄与します。これらの施策を通じて、「働きがいのある職場」の演出や従業員定着率の向上が期待できます。
なお、インナーブランディングの事例はこちらの記事で詳しく紹介しています。
アウターブランディングに貢献する施策
一方で、ホークスのスポンサーメニューは、社会的認知度やブランドイメージを広く高めるアウターブランディングの側面も強みです。プロ野球の人気とスタジアムのスケール感が合わさることで、数万人規模の来場者と数百万規模の視聴者にリーチできます。
▼大型ビジョンへの企業ロゴの掲出

大型ビジョンは、スタジアム内外の目立つ位置に設置され、試合中継やニュース映像にも映り込みやすい媒体です。来場者だけでなく、テレビやSNSなどを通じて全国のファンに企業ロゴを届けることができます。視覚的なインパクトが大きく、ブランド認知を高める効果があります。
▼ユニフォームへの企業ロゴの掲出

選手が着用するユニフォームは、自然にロゴを露出できる広告手段です。試合映像や写真に繰り返し登場するため、継続的なブランド想起につながります。企業とチームが一体となって取り組む姿勢を示し、ファンや視聴者に親近感を感じてもらえることができます。信頼性や好感度を高めるシンボリックなブランディング施策です。
▼地域コミュニティとの関係構築・活性化

ホークスが展開する福岡・九州の地域貢献活動に協賛することで、「地域に根ざした企業」という好印象を獲得できます。CSR活動とブランディングを両立させ、企業の社会的価値を高められます。こうした取り組みは、単なる知名度向上にとどまらず、「企業姿勢そのもの」を発信する場となり、BtoC・BtoB双方での信頼構築へとつながります。
なお、アウターブランディングにつながるCSR活動のメリットや取り組みの詳細はこちらの記事で解説しています。
まとめ
この記事では、インナーブランディングについて以下の内容を解説しました。
インナーブランディングとアウターブランディングの違い
インナーブランディングの進め方
インナーブランディングの施策例
インナーブランディングの効果測定とフィードバックの重要性
福岡ソフトバンクホークスのインナー・アウターブランディングに貢献する施策
インナーブランディングとアウターブランディングは、対象も目的も異なりますが、どちらも企業価値向上のために欠かせない両輪です。従業員が理念に共感し、誇りを持って働ける環境を整えることで、外部へのブランド発信に説得力と一貫性が生まれます。
『福岡ソフトバンクホークス』では、認知度向上やブランドイメージの強化、新たな顧客の獲得などさまざまな目的に活用できるスポンサーシップのメニューを用意しています。
詳しくはこちらの資料をご確認ください。