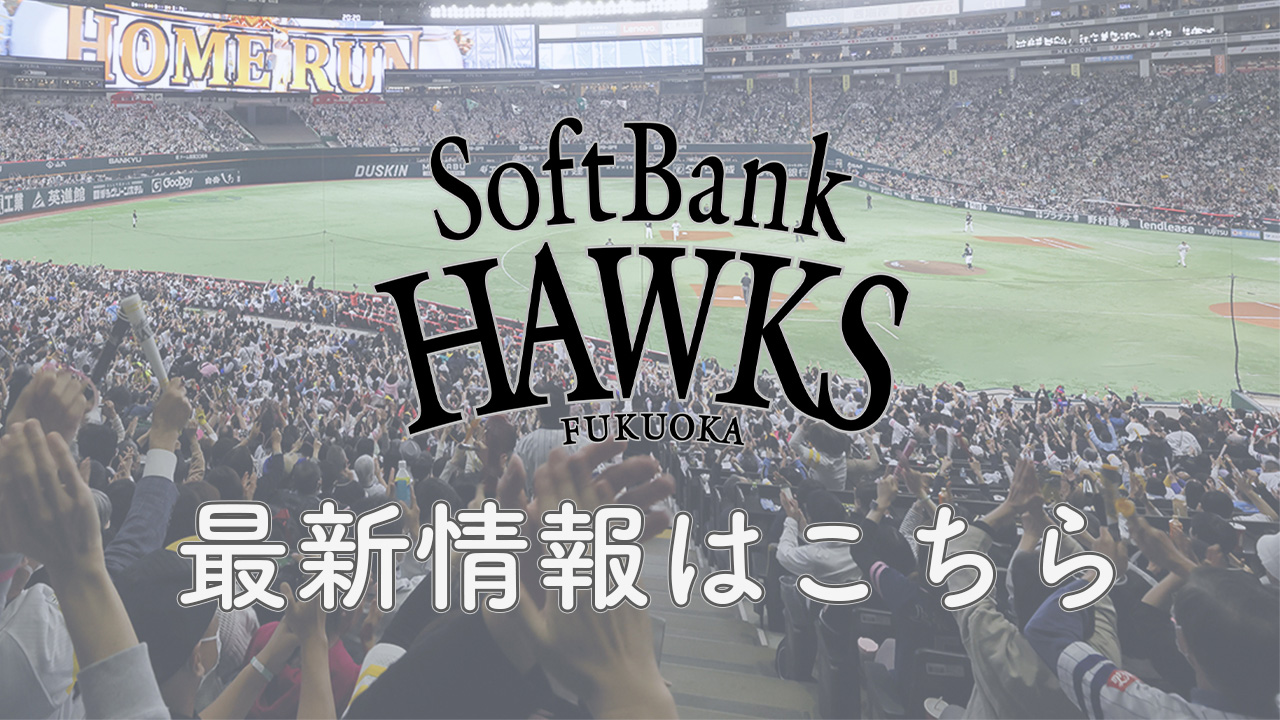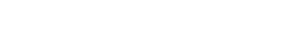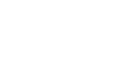福岡ソフトバンクホークス球団会長の王貞治が「世界の子供たちを繋げて、野球の輪を広げたい」という大いなる夢を掲げて「世界少年野球大会」(WCBF)をスタートさせたのが1990年(平成2年)のこと。コロナ禍で2020年(令和2年)から4年間の中断期間を挟み、2024年(令和6年)に再開。節目の第30回大会が福岡・大野城市を中心に県内の9市町で第30回大会が開催されたのに続き、第31回の今夏は、7月30日から8月7日までの9日間、秋田・大仙市で行われた。
今大会にも11か国・地域の子供たちが参加しているが、渡航費、用具、練習着などの諸経費はすべてWCBFが負担。福岡ソフトバンクホークス株式会社、ソフトバンクグループ株式会社も、このWCBFの活動に賛同、協賛している。
そして、85歳の王は、連日の猛暑もどこ吹く風とばかりに、連日のようにグラウンドに立ち、子供たちに声を掛け、質問に答え、ハイタッチも交わし、精力的な日々を送っていた。
「昨日より今日、今日より明日。子供たちは一日一日伸びていくわけだからね」
グラウンドで、さらにグラウンド外でも多くの経験を積み、国や人種の壁も超えた交流を重ねながら、日々、心身ともに成長していく子供たちの姿を、心の底から嬉しそうに見つめる王の姿がそこにはあった。時代を超えて続く、王貞治の“ライフワーク”ともいえる今大会に込める思いと、ここから育っていく子供たちが担う『未来の野球界』への期待と展望を聞いた。
(※故人以外は敬称略)
王が巨人監督を退任したのは1988年(昭和63年)で、ソフトバンクの前身・ダイエーの監督に就任するのは1995年(平成7年)。だから、この「世界少年野球大会」がスタートした1990年(平成2年)は、次なるステップに備える“充電期間”でもあった。
ユニホームを脱いで、どうしようかというときに、じゃあ、果たして自分は何をしたらいいのか。普通、一般的には何か仕事をやるとか、なんだろうけど、僕はあんまり器用じゃないしね。だからやっぱり、自分自身が一番得意な部分で、子供たちに自分が味わった“いい思い”を、少しでも子供たちにも味わってもらいたいと思ってね。
そういうことをするんだったら、ハンク・アーロンさんとも交流関係もあったし、僕も『世界の王』なんて言われたりしていたもんだから、だったら、日本だけじゃなくて、世界の子供たちをつなげていくという意味を含めてスタートしたんですよね。
メジャー通算755本塁打のハンク・アーロン氏は、2007年(平成19年)にバリー・ボンズ(サンフランシスコ・ジャイアンツなど)に抜かれるまでの33年間にわたって、メジャー歴代トップの本塁打記録を保持していた。
この「755」を、ボンズよりも先に上回ったのが王だった。
日米のレベル差、球場のスケールの違いなどを挙げ、王の記録を無視するかのようなメジャーの風潮も一部にはあった中、アーロン氏は祝福と交友の証として、王の「一本足打法」が、そのフォルムからの連想で「フラミンゴ打法」と呼ばれていたことから、フラミンゴのはく製を“世界記録更新”に際して贈呈するなど、互いをリスペクトしながら、2人の交流は深まっていった。2006年の第1回WBCで王は日本代表監督を務め、日本を世界一に導いているが、その決勝戦はアーロン氏の始球式で始まっている。
その日米球界のレジェンドがタッグを組んで立ち上げたのが、この「世界少年野球大会」だった。2021年1月22日、アーロン氏は86歳でこの世を去ったが、王はその遺志を継ぎ、85歳になった今年もその歴史を積み重ね、31回目の開催にこぎつけた。
その情熱の源は「野球がまだ、世界のスポーツになっていないから」だと強調する。

サッカーはすごく大きな大会、ワールドカップとかをやっているじゃないですか。野球の場合は、ごく一部の人たちにとってはすごく熱狂的なスポーツになっているんだけど、僕はやっぱり、もっともっとアジア、ヨーロッパ、アフリカ、南アメリカといったところから、どんどんチームが来てほしい。そうならないと、世界のスポーツとは言えなくなっちゃうからね。
今年は、アフリカからブルキナファソが初めて参加してくれた。そういう国の子供たちを見ていても、個々の力という点では、身体能力はすごくある。そういった子供たちに、これからも野球をやる機会を提供することで、その子たちの能力をどんどん引き上げてあげたいと思っているんです。いずれにしても、子供たち同士、アジアの子、アフリカの子、ヨーロッパの子、いろんな国から来た子供たちとの接点を作ってあげる。今の時代は、きっかけを作りさえすれば、メールとかで情報交換をしたりするから、世間も世界も、ものすごく狭くなる。人間同士のコミュニケーションが増えるから、もめごとだって少なくなると思うんですね。
大人だと何だかんだあるんだろうけど、子供同士っていうのは、ホントにわだかまりなく、すっと仲良くなる。秋田に来てから、もうかなり(それぞれの距離が)近くなっているんじゃないかな?最後(のお別れ)はいつも、涙、涙になっちゃうんだけど、そういう“子供的な思い”というのがあれば、戦争だって起きないはずなんですよ。
今回、ブルキナファソが初参加したことで、過去の大会から累計して、この「世界少年野球大会」に参加した国・地域がちょうど「100」になった。
言葉、人種、国境。
そうした多くの“壁”を「野球」という共通言語で、ともに乗り越えてほしい。それは王がアーロン氏との長き交流と友情を通して得た、何物にも代えがたい心の財産でもある。
だから、王も炎天下のグラウンドに立ち、子供たちの輪の中にどんどん入っていく。子供たちの方も、何の迷いも遠慮も忖度もなく、王のもとへ近づくと、ハイタッチを求め、握手を交わし、取り囲んで質問攻めにするのだ。
この大会を始めた頃は、聞いてくる子供もほとんどいなかったんだよ。でも、今の子供たちは、どんどん聞いてくるよね。
王は、そうした触れ合いが実に楽しそうだ。だから、子供たちの無邪気な、ストレートなどんな質問にも、決してはぐらかしたりもしない。
子供たちに答えるときのその表情は、まるで監督時代に、ホークスの選手たちに教えていた時のように、真剣そのものだった。
―王さん、どうやったら、ホームランを打てるんですか?
それはね、走ってね、地面についているところを強くしなきゃいけないんだ。地面についているところはどこだい?足だろ?足で打つんだ。打ちたい、打ちたい、ホームランを打ちたい、力いっぱい打つっていうんじゃなく、足を使うんだよ。
ステップして、グリップを振り下ろすジェスチャーを交えながら、下半身の重要性を力説する。それはちょっとばかり、小学生レベルでは難しいのでは、と傍で聞いていたこちらは正直、感じたほどだった。
グラウンドに立つと、王の心も体も完全に“野球モード”になり、燃えてくるのだろう。
日々の野球教室は、世界11か国・地域から参加した95選手を4組に分け、投、打、守、走のセクションを時間ごとに区切って巡回していく。8月2日の指導時、王は『走』のフィールドに立っていた。
野球っていうのは、出ている人が絶対、ヒーローになるチャンスがあるわけですよ。自分の打席って、絶対に回ってくる。ランナーがいなかったりする時もあるから。
その喜びを、子供たち全員に味わってもらうという“疑似体験”なのだろう。王が熱視線を送っていた『走』セクションの試みは、実にユニークだった。
一塁への駆け抜けなど、ベースランニングの練習を一通り行った後、コーチが提案したのは「ホームランを打った時の練習をしましょう」。
スイングをして、ホームラン。走りながら、ヘルメットを両手で天に突き上げたり、ガッツポーズをしたりするのも、それこそ何でもあり。喜びながらダイヤモンドを一周し、ホームで仲間たちの出迎えを受け、ハグを交わし、ハイタッチをする。打った喜びをチームメートたちと分かち合う。それこそ、ヒーローになる醍醐味を味わってもらうのだ。
王は、炎天下のグラウンドで、三塁ベース付近に立っていた。
子供たちが、笑顔で走ってくる。王が上げた左手に子供たちがタッチをして、本塁へと向かっていく。その「野球をやる喜び」を、子供たちに感じてもらいたい。
だから王は、ヒットを打てなかったある少女のことを、ずっと気にかけていた。
今大会が初参加のブルキナファソは、世界でも「最貧国」に分類され、国内では野球道具も満足にそろわないという事情もある。男女合わせて5選手が来日したが、練習でもグラブをはめてボールを追う姿は、どこかしら、まだぎこちない。
8月2日の練習でのことだった。
そのブルキナファソから来た一人の女の子が、ゲーム形式での6打席で、一度もボールがバットに当たらないまま、時間切れになった。
あの女の子が、打てるようになってほしいんだ。この大会が終わるまでに、何とかヒットを打ってほしいよね。
王は、その“6タコ”を、心の底から悔しがっていたのだという。
そのブルキナファソの少女は、翌3日のゲーム形式での打席で、見事にセンター前ヒットを放った。仲間たちも大喜びで、次々にハイタッチが起こり、歓喜の輪ができた。
体調を考慮し、適宜、冷房の効いた部屋で休息を挟むため、王は残念ながらそのヒットを打つシーンを直接は見られなかった。しかし、王がその女の子のことをひたすら気にしていたことを、大会に携わるスタッフたちは、全員が分かっていた。
「あの女の子、打ちましたよ」
その報告が、休憩中の王のもとへ届けられると、王は急いでグラウンドに出てきた。その彼女を探して歩み寄っていくと、話し掛け、祝福のハイタッチを交わした。
今回、初めて“運営側の一人”として参加したソフトバンクCBO(チーフ・ベースボール・オフィサー)の城島健司も、ヒットが打てたというブルキナファソの少女の話をしていた時の王が「仏のような目をしていたんですよ」と、その印象的なシーンを語りながら、思わず、顔をほころばせた。
子供たちの、そうした“日々の成長ぶり”が、王はたまらなく嬉しいのだ。

王のダイエー監督就任が決まった直後の1994年秋、ダイエーがドラフト会議で1位指名したのが、大分・別府大付高(現・明豊高)の捕手・城島健司だった。王のもとで日本を代表する捕手に成長し、メジャーの舞台でも戦った城島にとって、その師弟の絆はもちろんのこと、王貞治という偉大なる野球人へ向ける敬愛の気持ちは強い。
「この大会は、会長が35年、ずっと続けられていること。ホークスとしては、誰もそこに行かないなんて、それはできませんよ」
この夏は、1軍が日本ハムとの激しい首位争いを展開中だ。1軍から4軍まで、各軍の状況と、全120選手の調子や実力を把握した上で、戦力の入れ替えなどを調整する「コーディネーター」を束ねるトップでもある城島が、この時期に現場を離れるのは決してベストのタイミングではない。それでも、球団が掲げる『王イズム』の継承という観点に立てば、王がこの大会に込めた野球の振興、子供たちへ野球をやる喜びを伝えたいという『思い』をしっかりと受け止め、次世代の野球界、未来のホークスへと伝承していくことも、それこそ王の愛弟子である城島に課された、重要なミッションでもある。
「今年でいえば、僕が一番適任。当然、だから行く気でした」と城島は、今大会への参加を球団に直訴したという、その決断に至る背景を説明してくれた。
「会長は、なんなら『あとはみんなでやっといてくれ』でね、最初と最後だけ出て来てもいいんですよ。そうじゃなくて、率先してやっているのがすごいなと思うし、それも苦痛じゃなさそうにしているんですよ。ホントに楽しそうですもん」
師の情熱に改めて触れた城島は、今大会への参加と視察を通し、王が四半世紀以上も前から、野球界の『今』を見通していたかのような“先見性”に、改めて気づかされたという。
「少子化とか野球人口の問題で、今、その危機になっていて、だからこういう大会を始める、というなら分かるんですよ。僕らにとって、それは球団を強化していく上ですごく大きな問題なわけですよ。120人の選手を抱えて、チーム作りをしていかなきゃいけない僕らが直面している問題に、早めに手を打ってやっていたというか、そこら辺の嗅覚、感覚というのは、ちょっと頭が下がります。35年前は多分、そんなことも言われてなかったと思うんです。その時から始めているんですから、僕はあの人、宇宙から来たんじゃないか、未来から来たんじゃないかな、って思うくらいなんですよ」
運動神経のいい男の子は、こぞって「野球」をやるというのが、それこそ昭和時代であれば、半ば当たり前の風潮でもあった。しかし、今やサッカー、バスケットボール、ラグビーや卓球など「子供たちがやるスポーツを選べる時代ですよ」と王は強調する。
少子化という社会問題に加え、こうしたスポーツや趣味の多様化も大きく影響しているのだろう。日本高校野球連盟の発表によると、2025年度5月末現在、高校の硬式野球部の加盟校は20年連続減少となる3768校で、2005年(平成17年)のピーク時だった4253校から20年で500近く減少。さらに部員数も11年連続減少の12万5381人で、こちらもピーク時の2014年(平成26年)の17万312人から約5万人減で、全国でも36道県で部員数が減少したという、衝撃的な数字がずらりと並んでいる。
日本の野球界をピラミッドで表現すれば、頂点がプロ、その下に社会人、独立リーグ、さらに高校、中学と続いていく。だから「世界少年野球大会」に参加している小学生らのジュニア世代は、それこそ土台部分にあたる。そのすそ野が広がり、しっかりと根を下ろし、基礎が固まらなければ、その上部がぐらついてしまうのは自明の理だ。
野球人口が減りつつある。これを、いかにして食い止めるのか。その危機感を実感している城島も、師に負けず劣らずの熱量で、子供たちと真正面から向き合った。

8月3日に市内の中学校で行われた野球教室は、午後1時半からの開始予定だった。
ところが城島は、その30分前に会場へ到着すると、いきなり指導を始めた。30人近い参加者一人一人に、ティー打撃でアドバイスを送るための時間を確保するための“前倒し”は、自らも中学時代に参加した野球教室で、王から直接、アドバイスをもらった喜びを忘れていないからだ。
「自分も、プロ野球のフロントの、ちょっと立場のあるところに今年から来て、このタイミングでこの大会に参加したんですけど、俺だって野球を始めたときは、土曜日とか日曜日に、早く試合にならんかな、とか思って始めたんですもん。なんか、どうしても、上に行けば行くほど、苦しかったりすることばかりが目に入るんですよ。でも、野球って、根本的には楽しいもの。その“ベース”をここで見られて、チーム作りにももう一回、腰が入るというか、ちょっと気合入りましたよ。僕にとってはホント、ここへ来てよかったですよ」
その『野球をやる喜び』を伝えることが、王が時代を超え、長い時間をかけて育ててきたこの大会の、最大の意義でもある。
王も、愛弟子の“気づき”を、心から歓迎した。
城島君は今、監督、コーチという立場じゃない。選手の素質を見ながら、チームに必要な選手とか、野球の、ホークスの将来ということも考えてくれているんだけど、今回のこの大会に参加してくれるというのは、すごくいい勉強になると思う。彼は今、フロントの立場にあるから、野球の見方も現役の人たちの見方とは、ちょっと違うわけですよ。そういった意味では、野球界をもっともっと広げていくという意味で、彼のアイディア、考え方というものを大いに参考にしたい。まず実態を見てもらった上で、もうちょっとこういうことをした方がいいんじゃないかという意見を言ってくれればいいな、と思っています。
時代の推移とともに、野球界が直面する“問題の質”も変わってくる。
子供たちに、野球を思い切りやれる『場』を与えてあげたい。
「野球」を通して、スポーツの楽しさを知る。仲間たちと力を合わせて、1つのボールを追いかけ、勝利の喜びを分かち合うその姿勢は、成人し、社会に出たときには必ず、その体験が生きてくる。
その「楽しさ」と「尊さ」を味わえるのがスポーツの、そして「野球」の醍醐味でもある。
この好循環を生み出すためのきっかけを作り、その媒介となりたい。王は、その“願いのバトン”を、着実に次世代へとつないでいきたいのだ。
今、校庭でバット振っちゃいけないとか、公園でキャッチボールをしちゃいけないとかっていう、我々からしたら、なんでそうなっちゃったのかな、というような規制があったりするんでね。それをもう一回、そういう立場の人たちともいろいろと話し合いながら、野球をやってもいい、っていうのを少し緩やかにしてもらいたい。子供たちがかわいそうじゃないですか。やっぱり、子供たちが野球をできるような環境をまず取り戻したいんです。
野球は、明治時代から日本で続いてきて、人気にもなった。やっぱり僕は、野球って日本人に向いたスポーツだと思うんですよ。今、大谷(翔平)君があんなに活躍してくれている。メジャーリーグでトップの選手が日本人で、それをアメリカ人だって認めてくれているわけですよ。だから、将来的にどういう選手が出てくるかなんて今は分からないんだから、その期待を持ちながら、子供たちに野球をやってもらいたいし、そういう状況を作ってあげたいんです。
85歳の夏。
「世界の王」の野球への情熱は、この夏の猛暑などにも決して負けない“強さと熱さ”にいまなお、満ち溢れているのだ。
(取材・文 スポーツライター・喜瀬雅則)
試合情報
チーム情報
ファーム
チケット
イベント
ファンクラブ
グッズ
グルメ
みずほPayPayドーム情報
スポンサー
スクール・ジュニアチーム
エンタメ
会員限定コンテンツ
Language
会社概要
採用情報
CSR活動
問い合わせ







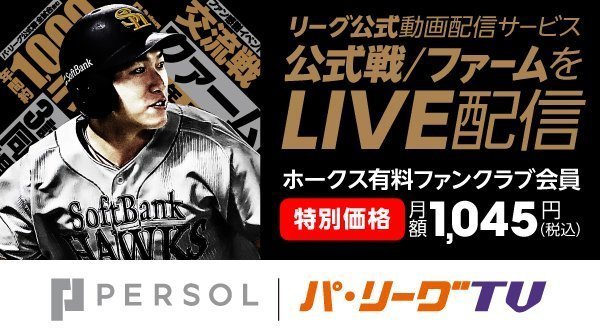




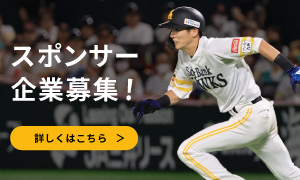

 ログイン・会員登録
ログイン・会員登録 チケット購入
チケット購入 試合情報
試合情報 チーム情報
チーム情報 ファーム
ファーム イベント
イベント ファンクラブ
ファンクラブ グッズ
グッズ グルメ
グルメ みずほPayPayドーム情報
みずほPayPayドーム情報 スポンサー
スポンサー スクール・ジュニアチーム
スクール・ジュニアチーム エンタメ
エンタメ 会員限定コンテンツ
会員限定コンテンツ Language
Language 会社概要
会社概要 CSR活動
CSR活動 問い合わせ
問い合わせ